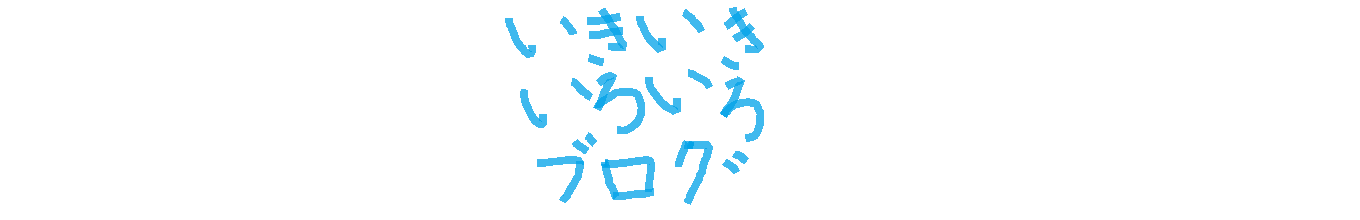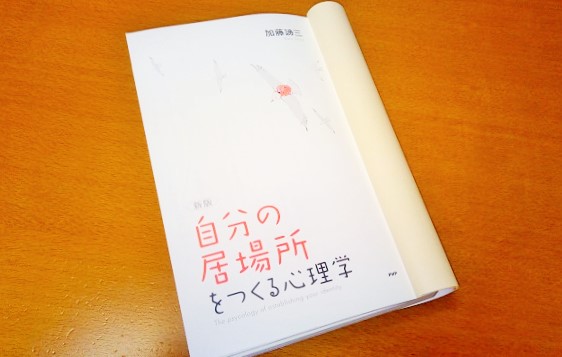
ほとんど国内での引っ越しですが、幼少期に都会から田舎への引っ越しが続いたせいか、よそ者扱いを受けたり、のけ者にされたりすることが度々ありました。
各集落に独特の文化があったのかもしれません。
また、引っ越し続きで両親にも余裕がなく、自宅でものけ者・邪魔者扱いされ、居場所がなかった記憶があります。
そして、そうしたよそ者・のけ者・邪魔者扱いが、いつしか自分の中で「当たり前でありながら、とても恐い」ことになっていった気がします。
自分の存在に信頼がもてず、居ても居なくても関係ないような生存感覚がずっとぬぐえなかったのか、
自宅近くの溜池のほとりに座って、キレイな石を拾い集めながら「このまま池に入って消えてしまいたい」とよく思っていました。
そんなことをこの歳になっても覚えているくらいなので、よほど強くそう思っていたのでしょう…
約10年住んだ実家と呼べる家には、1人暮らしを始めた後も何度か帰省したことがありますが、
結局最後まで自分の居場所があるとは思えませんでした。
その原因は、幼少期に親から関心をもってもらえず、のけ者や邪魔者扱いされていたことも関係していると思います。
『「自分の居場所」をつくる心理学』(加藤 諦三、2010)で、
自分が自分の属する集団に実際の自分として受け入れられていると感じるかどうかに、その人の性格はかかっている。(p4)
という文章がありますが、、、
実家暮らしの頃は、素の自分では親に受け入れられないと無意識のうちに感じていたため、気兼ねしたり、しつこくなっていたり、しがみついたりしていた記憶があります。
今考えるとそれは、心に極度の愛情欲求を持っていたためであり、素の自分では親から受け入れられないと思っていたため、
自己実現を犠牲にする、自己主張を犠牲にする、自分であることを止める、愛されるためなら自分でない自分を演じる(p4)
ことで、親から無理やり愛情を得ようとしていたからではないかと思います。
と同時に、
自分の甘えを表現したら相手に拒絶されると思う(p4)
気持ちも強く、
素の自分では親に甘えることができずに、親への甘えを抑え続けていた気がします。
「親は忙しい、親は病気だから」と、甘えの感情を抑圧しながら心にフタをし、
世間的に評価される人間になることを目標として生き続けていました。
その結果は、他の記事で書いた通りです。
甘えの欲求が満たされていれば人は素直になって、何も頑固になる心理的必要性もない。意地を張る必要がないということである。気兼ねとか頑固とかしつこさというのは、どこかでつながっているように思う。(p5)
心の底にのけ者意識があるからこそ気兼ねするのである。甘えられないのである。(p5)
この「のけ者意識」が無くならない限り、他人に甘えることはできず、素直にもなれず、いつまで経っても気兼ねする人間関係を築いてしまうようです。
子どもの頃、心優しい友人が体を心配してくれたとき、意地を張って素直になれなかったことを思い出しました…
いつも今のままの自分ではいけないと感じている(p24)
という口唇的性格を、以前の私は強く持っていた気がします。
燃え尽きるまで仕事をしていても満足できず、仕事依存症で仕事で結果を出さないと自分に価値がないと思っていました。
しかし、
今のままの自分で素晴らしいと感じられる人は趣味を持ち、人生を楽しめる。生きることに喜びを感じられる。(p27)
というように、今の自分や素の自分を受け入れることができてはじめて人生を楽しめる、と今は思えます。
数年前までは趣味もなく、人生を楽しむという次元とは違った刹那的なところにいた気がしますが…
今は「こうゆうのを趣味というのかな」と思えるようなことをいくつかやって、毎日を楽しんでいます。