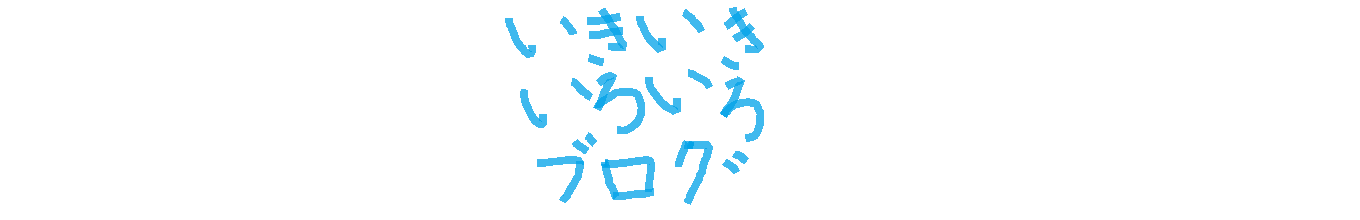で書いた『心の休ませ方』(加藤諦三、2006)の内容について、もう少し書いておこうと思います。
前回の内容以外に、特にインパクトを覚えた箇所として、
愛情飢餓感が強いと、他者からの評価を得ようと無意味な努力をしてしまう
という部分がありました。
他者からの評価を欲する理由
短期的には、それが「仕事ができる人」や「結果を残せる人」というような仕事上の高評価に繋がる可能性もあるかもしれません。
が、長期的にみればあまり好ましい状態とはいえないと思っています。
それだけ他者からの評価を欲するのはなぜなのかを考えてみる必要がある、と思うからです。
過去、他者からの評価を得るために、好きでもない仕事で社畜になり果てた時期がありましたが……
それも今思えば、幼少期に満たせなかった幼児的願望が影響していると分かります。
幼児的願望が満たされず愛情飢餓感が強いまま生きていると、他者から拒否されるのが怖いために必要以上に周囲に迎合してしまいます。
過剰適応と言うのでしょうか…
その結果、本音ではない言動・行動をとりがちになり(自分の気持ちが分からなくなり)、
自分に対して不誠実な言動・行動をとり続けてしまうようです。
自分を大切にできない
結果として、心身ともに限界を超えて酷使してしまうことになります…
が、それでもなお本人は愛情飢餓感が強いままなので、自分に対して不誠実な生き方を貫いてしまいます。
それは自分を大切にしない、自分を守らない、自分の心身の健康をかえりみない生き方です。
それゆえ、
「頑張ることも生きることだけれど、休むこともまた生きること」(前褐書、230項)
だと気付き、
努力や頑張りだけでは物事は解決しないこと、これまでの生き方が間違っていたことを真剣に認識する必要があります。
それと同時に、自分の人生を生きるエネルギーを取り戻すために、これまで抑圧してきた憎しみの感情を吐き出す必要があります。
自分をケアする能動的な姿勢
ただ、幼児的願望と愛情飢餓感が強いことを自覚して、憎しみの感情を吐き出しただけでは、頑張りすぎてしまう自分に変わりはありません。
他人に対する自分の態度、他人に対する自分の感じ方、自分に対する自分の感じ方などを変えることができてはじめて、心理的離乳は完成したと言えるのではなかろうか。そうなってはじめて本当の自分になれたと言える(『自分に気づく心理学』加藤諦三、2000、216項)
とあるように、自分で自分をケアしつづけていく能動的な姿勢が不可欠です。
抑圧した感情を吐き出し、幼児的願望と強い愛情飢餓感を自覚し、自分で自分を満たせるようになること…
大人になってから幼少期の愛情欲求を満たすのは、並大抵の覚悟ではできない、辛く苦しい行為です。
ですが、その行為は頑張りすぎてしまう自分を変える重要な方法の1つだと思います。