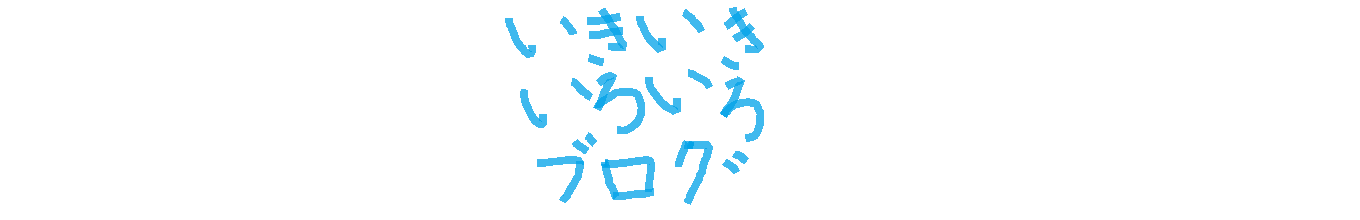30数年で10回以上引っ越しをしてきましたが、生まれてから2回目の引っ越しで都会から田舎へ移住することになりました。
断片的に当時の記憶があるのですが、移住先へ向かう新幹線車内で喫煙車両から煙が出ており、
その臭いが禁煙車両に流れてきて、他の乗客が食べていた幕の内弁当の匂いと混ざって気分が悪くなったことを覚えています。
地域で除け者扱い
移住先は、山の中の限界集落地域にあったボロボロの家。
狭い集落の同世代は同性ばかりで、いつの間にか仲間外れにされていて、友人宅に私だけ上がらせてもらえないことがよくありました。
ボロボロの家に住み始めたよそ者だから嫌われているのかと思っていましたが、後になって祖父の土地問題で揉めていたことを知りました。
そんな経緯からか、隣の集落の男の子たちと川や田んぼで遊んでいた記憶のほうが強くあります。
自分の存在が信頼できない
保育所へ通い始めたのですがまったく馴染めず、保育所敷地外にある民家の畑の淵に座っているか、
保育所で飼っていたうさぎ小屋でうざぎと遊んでいました。
保育所敷地外にいることで、保育士さんからよくたしなめられていた記憶があります。
小学校入学後は登校班の上級生にいじめられ登校拒否になったり、食欲不振による貧血で倒れたり、
どうも生命力の弱い感じがありました。
自分の存在が信頼できない感覚で、学校以外ではよく自宅近くの溜め池のそばに座っていました。
やっと自分が出せるようになるも
中学校では運動部へ加入したせいか元気になり、好きなことが見つかったような気持ちがしました。
ただ、1番仲が良いと思っていた友人に裏切られて人間不信となり、嫌われることが怖くなりました。
それでも「学費の安い地元の公立高校へ入学する」ことを目標に、
学業・部活動・学内活動で内申点を稼ぎながら、乏しい脳をフル稼働させていた記憶があります。
ただ、その頃は交感神経優位で寝ている間も緊張状態が続いており、
成長期にもかかわらず3~4時間くらいしか眠れていませんでした。
心を犠牲にしていた
それくらい「心」を犠牲にしながら感情にフタをしないと生きられない環境だった、と今なら分かります。
当時は時間が過ぎるのが異様に速く、毎日が秒で過ぎていきましたが今考えると異常でした。
それと当時は慕っていた人が自死したり、友人が精神病になったり、親の病気が悪化したり…つらいことが続きました。
高校入学後は自分で学費を払って通っている子がいたり、すでに自立した考え方を持っている子が多くいたりして、自分の心の幼さを感じることが多くありました。
それまでに心を犠牲にしてきたため、年齢に合わせた情緒が育っていなかったからだと後に気づくのですが、
当時は知る由もありませんでした。
情緒未成熟のまま
育った環境に愛着がなかったため、高校卒業後はそれまで貯めたお金を持って遠く離れた地へ。
それから数年前までの約15年間はいわゆる怒涛の日々でしたが、、、
そうなったのは情緒の未成熟と無関係ではないと思います。
個人的に思うのは、年齢に合わせた情緒をその時々にしっかり育まないと、
後から育もうと思っても手遅れということです。
心を犠牲にしたツケ
子どもの頃に感じるであろう、楽しい、嬉しい、悲しい、寂しい、くやしい、苦しい、辛い、おかしい、ムカつく、羨ましい、怖い、嫌い、すごい、むなしいなどの各感情。
それの感情はその時々で抑圧せずにしっかり感じながら、心で受け止めながら、心に痛みを感じながら、
時間の中で育む必要があると思います。
それらの感情を無理やり抑えたり、自分を守るために偽ったりして、覚えるべき感情から逃げていると、
そのうち自分の感情が分からなくなります。
子ども時代に満たすべき欲求
また、親に甘える欲求。
これを抑圧したまま満たせずにいると、社会人になって燃え尽きたり、うつ病になったり、
パワハラ・セクハラ・モラハラに上手く対応できなかったりする可能性が高いです。
実家を出るまで「今辛くて苦しくても、きっと将来はマシになる」となんとか希望を捨てず、
歯を食いしばって生きていましたが、、、
努力する方向を間違い、心の成長を犠牲にして生きただけでした。
でも当時はその努力以外、自分を守る方法、生きていく術を知らなかったのです…
今から取り戻すのは困難だと思いますが、犠牲にした情緒の成熟を一生かけて行おうとしています。