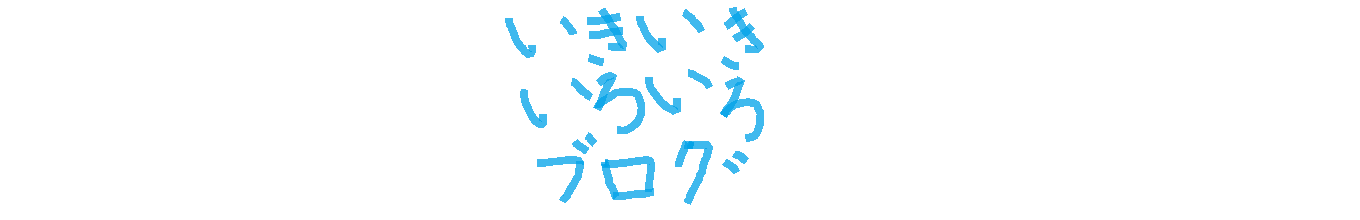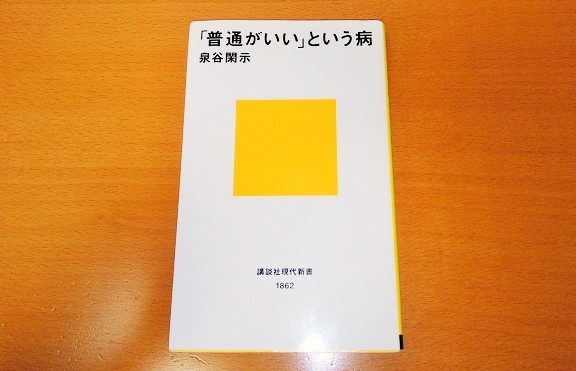
多数派ではなく少数派なら、大通りよりも小道を行く【前編】の続きです。
大通りを行くのがマジョリティ。マイノリティの人は、どこかで大通りから外れる。「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る」という彫刻家で詩人としても有名な高村光太郎の言葉がありますが、まさに道のないところを行くわけです。細い小径、一人通れるだけの道です。ここは一々障害物があったりして、「こっち行こうか、あっち行こうか」と自分で判断をしながら一つ一つ選択して、道なき道を行かなければならない。これがマイノリティの道です。
一方、マジョリティの大通りでは、「みんなも行っている。みんなそうだから私もこれでいいんだ」と思って、自分自身では判断を行っていません。また、この道がどこに向かっていくのかも知らない。そういう意味で自分の人生に責任を持っていないし、自分の人生にもなっていないわけです。
~中略~
マジョリティの大道りは、不自然で窮屈な道です。人間はそれぞれユニークな存在なのですから、本来一万人いたら一万通りの道なき道があるはずです。にもかかわらず、大勢の人が通る大通りというものがあること自体、とても不自然なことです。
大通りを歩くということは、いろんなことを諦めたり、感じないように麻痺していたり、すなわち去勢された状態で歩いているということです。そうでもなければ、苦痛で歩けたものではありません。しかし、それでもなぜ多くの人間がそこを歩きたがるのか。どんな人だって、本当は自由でありたいはずなのに。(p210~212)
この現象について著者は、エーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』という本に書かれたエッセンスを抽出して説明しています。
自由というものは、なんの指針もなければ、その小径が正しいのかと問われても答えようがないもので、自分の判断以外に当てに出来るものはない。マニュアルもなければ他人との比較も出来ないし前例すらない。これが自由ということの大変さなのです。そして多くの人は、このリスクが怖くてしょうがない。それに比べて、大通りは不自由だけれど安全。これが、人々を大通りに強くひきつけている最大の理由であるということなのです。
大通りの人たちは、必ず徒党を組みます。彼らは、内に不自然さ、窮屈さを無意識的に抱えているので、どうにかしてそれを打ち消しておく必要がある。そうでなければ、自分たちの大通りが間違った道であるということがバレてしまう。打ち消すには、井戸端会議的に徒党を組むのが一番手っ取り早い。「ね、そうよね。私たち正しいわよね。あの人はちょっと変よね」というようなことを言って、大通りを外れた人のゴシップをネタに、自分たちを正当化して安心するわけです。(p212~213)
大通りを行くのに安心感を覚えるのは、皆それぞれこの社会で生きていくことに不安があるからだと思いますし、
それだけ個人が守られていない社会である証ともいえるかもしれません。
ただ、そんな状態では真に生きているとはいえない、というのが著者の主張です。
考えてみると、組織が大きくなればなるほど構造も歪(いびつ)になっていくケースが多く、
そうした組織ではイエスマンの多数派ばかりが優遇されている印象があります。
それは多数派を優遇しておいたほうが都合の良い組織が、社会に溢れているからだろうと思いますし、
資本主義の構造自体がそういう感じなので仕方ないのかもしれません。
でも、本当にそういう生き方でいいのか?と著者は疑問を呈しています。
死を目の前にした時に、自分自身の生が不自然だったと思えてしまったなら、たぶん大変な後悔が訪れることになるでしょう。もちろん、誰しも死そのものについては想像することしかできないわけですが、この死という問題をきちんと見据えて生きることは、最後の瞬間にとても大きな違いを生むものではないかと思うのです。失敗も成功もすべてひっくるめて、自分らしい人生だったと思えるならば、納得のいく死に方ができるのではないでしょうか。
メメント・モリ、ラテン語で「死を想え」「死を忘れるな」という意味の言葉です。死というものを隣に置いてみてはじめて、今の自分の生きかたが本物なのか偽物なのかが照らし返され、明らかになる。だから、よく生きるために、いつも死を忘れてはならないという古くからの警句です。(p214)
個人的には、死に向き合う機会が多ければ多い人ほど、生き急ぐような傾向があるように思っていましたが、
それは、そうでない人よりも死が身近に感じられるからかもしれません。
さらに、著者はこうも述べています。
戦争をしかける国では、ほとんどの人が大通りを歩いているものです。そして、ぬるま湯のような生きている実感が乏しい状態の中で、どこかから正義という名の大義名分が登場して、「あの国に侵略されないために、先手を打ってこちらから攻めましょう」というようなことが言われ始める。すると戦争は反対だと考えていたはずの人までもが、自分の奥底で疼きだす何かに突き動かされて「平和のためだ。戦争を無くすための戦争だ」というスローガンに乗っかってしまうことも起こってくる。それが戦争なのだろうと思います。
ですから、本当の平和とはどうしたら実現するのかと考えてみると、みんなが一人一人の小径を行くマイノリティになることしかないのではないか。小径では、一人一人が生きること自体がメメント・モリになっているわけで、そうなれば国民の大多数が一つのイデオロギーやムードに支配され流されることは起こらない。それぞれ、自分が生きていること自体、明日死ぬかもしれないという自覚と緊迫感があるわけですから、誰もわざわざ戦争をしようとは思わなくなることでしょう。(p220、221)
著者は多数派として大通りを歩くのではなく、1人1人が小径を進んで少数派として生きることが、
結果として戦争回避にも繋がると述べています。
多数派となる巨大組織に属したほうが安心安全、という考え方は確かその通りだと思います。
でもそうでない価値観もあり、その価値観で生きていく自由もあります。
もちろん食べていかなければいけないのでキレイ事では済まされず、守るべき家族がいたとしたらそんな人生は歩めないかもしれません…
ただ、そんな環境でも社会の多数派に流されず自分の判断で障害物を乗り越えて生きているとすれば、
それはそれで道なきところを進んでいる少数派といえるのかもしれません。
「少数派であっても自分らしい人生を生きる」ことが当たり前の社会になってほしいです。