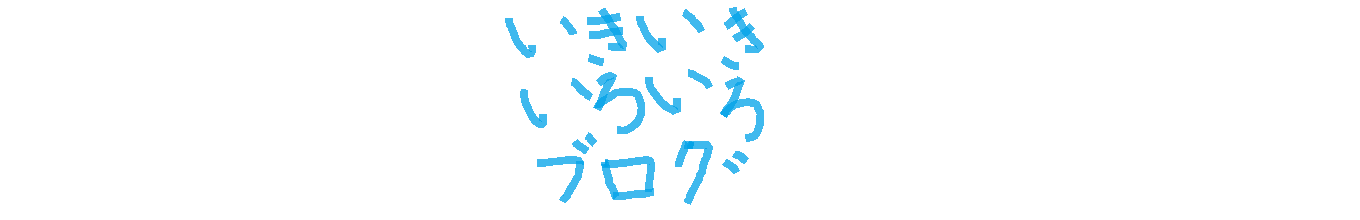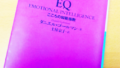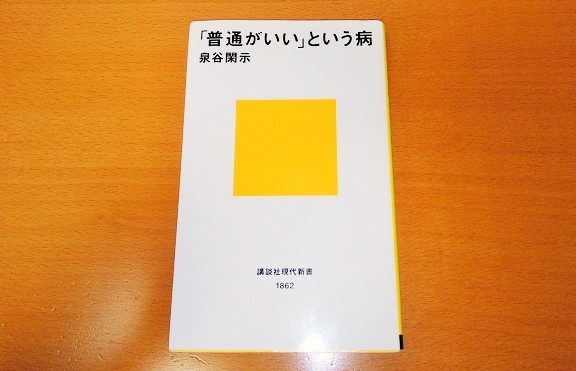
『「普通がいい」という病』の内容をしつこいほど繰り返し書いてきましたが、それも今日で終わります。
今回は著者が提唱する、螺旋階段を上るようなイメージで捉えやすい「人間の変化成熟のダイナミクス」という項目を抜粋。
これは本書に出てきた言葉によって、著者が成熟過程における各状態を整理したものです。
A.生まれたての状態。「本当の自分」のみだが、純粋でこわれやすい。「自分」という意識は未だない。
B. 徐々に社会適応のために神経症性や「偽りの自分」を身につけていく。しかし、時々窮屈さを感じた「本当の自分」が反発する。いわゆる反抗期。必死で「自分」を獲得しようとする。一人称を模索する。
C.反発の挫折と社会への屈服。「偽りの自分」に「本当の自分」が飼い馴らされる。社会適応が完成し、一人前の社会人になる。神経症性のピーク。「他者本位」。0人称。駱駝。
D.「本当の自分」が反逆を始めようと疼きはじめる。自分を見失ってしまったための苦悩が起こったり、心身の不調や、急に起こってしまう不適応などの形でシグナルが現れてくる。「他者本位」の行き詰まり。
E.「本当の自分」による革命動乱。溜め込まれていた怒りの噴出。一人称の実現。個人主義。「自己本位」。自力。獅子。
F.「自分」という一人称が消え、大いなる存在にゆだね、自然や偶然に身を開いていく。宗教的な意味での0人称。他力。小児。純粋さと強さの共存。創造的遊戯。
(p246、247)
従来の発達心理学などではCがゴールであるような考え方だったそうですが、
著者によればCは成熟過程であり、最終段階であるFから「第二の人生」を始めていくことが真に生きることだと指摘しています。
ただ現代社会では、Cで留まって人生を終える人が大半とのこと…
この分類を読んでいて、A~Dを経てきたのかな…と過去のことを思い返していました。
今後EやFへ進めるのかは分かりませんが、このままDで留まったりCへ戻ったりすることはできそうにないので、何とか道をつくって進みたいと思っています。
そうやって仮にFへ進んで自分らしく生きられるようになると、主語である「自分」が消えて、
天命とでも言うべき大きな力が自分を動かし、生かされていることに気付くとも著者は述べています。
個人的に、そうした宗教的な考え方には抵抗がありますが…
科学的には証明できない不思議な体験を何度もすると、目に見えない力を信じてしまうのと同様、
Fへ進むとそういう境地に達するのかもしれません。