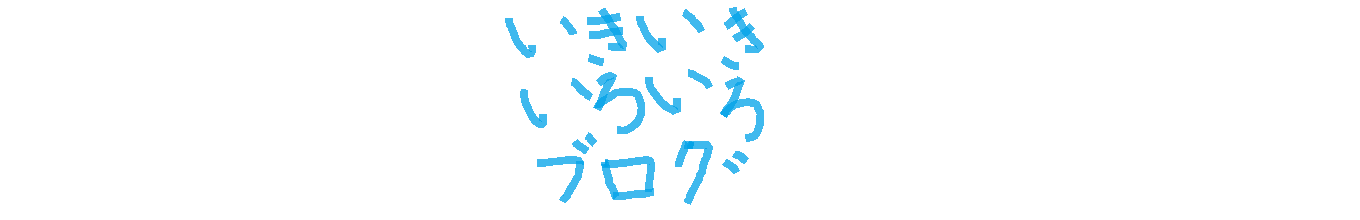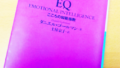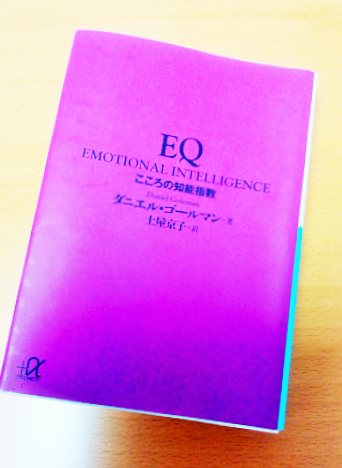
『EQ こころの知能指数』(ダニエル・ゴールマン、1998)に掲載されていたEQ5領域のうち、
今回は「2.感情を制御する」について紹介したいと思います。
なぜ感情を制御する必要があるかというと、何かの感情に支配され冷静さを欠いた状態では、
人間は物事を正確に見られなくなるからです。
「感情を制御する」ことについて著者は、
感情を適切な状態に制御しておく能力は、情動の自己認識の上に成り立つ。第五章では自分の感情を静め、不安や憂うつや苛立ちをふりはらう能力について考察する。また、感情の制御がうまくできない場合に起こる結果についても考える。感情をうまく制御できない人は、いつも不快な気分とたたかわなければならない。一方、感情をうまく制御できる人は、逆境や混乱からはやく立ち直ることができる。(p86)
と説明しています。
頭(浅い感情)ではなく、心(深い感情)に沿って生きるにもあったように、
「心」由来の深い感情「怒」を抑制してしまうと、他の「心」由来の深い感情(哀・喜・楽など)を認識できなくなってしまい(「心」由来の深い感情は、怒→哀→喜→楽の順番でしか表出できないため)、「頭」由来の浅い感情(=欲望)しか認識できなくなります。
それゆえ「感情の制御」とは感情を抑えつけることではなく、感情のバランスをとることだという前提を忘れてはいけないようです。
どのような感情であっても何かしらの意味・価値をもっているので、
マイナスと思える感情であっても抑制することは危険です(社会的には抑制することが良しとされていますが…)。
著者も、
感情を押し殺してしまうと、人間の感性は鈍麻し現実から遠ざかってしまう
と述べています。
私も感情を押し殺していた時期がありますが…そのような状態が数年間続くと、
いつのまにか自分の感情が分からなくなってしまい、自分の事なのに他人事のような人生を送ることになってしまいます…とになってしまいます。
EQ・(1)自分自身の情動を知るでも書きましたが、私自身は怒りの感情が沸いた際には冷静さを欠くことが多く、ブツブツと文句を言いがちです。
ただ、怒りの感情を抑圧し未処理のままだと、その後何らかのきっかけで一気にその怒りが爆発してしまうことが多い気がします。
なので怒りの感情が沸いた際には、爆発させないように上手く制御しながら冷静な状態へ持って行く、
というのが理想形なのかなと思っています。
怒りの感情をクールダウンするのに有効だと思っているのは、
- 「心の吐き出しノート」に怒りの感情を排出すること
- 時間を置くこと
- 怒りを覚えた対象と物理的距離を置くこと
などです。
特に、「心の吐き出しノート」に怒りの感情を排出する効果は絶大で、怒りの感情をコントロールするのに個人的には有効な方法だと思っています。
そうした物に頼らずとも、怒りの感情をうまく処理する心のゆとりを常備したいのですが、
精神的に成熟していないとなかなか難しいことでもあります…
ちなみに、あらゆる種類のストレスは、副腎皮質に働きかけて精神を緊張させた挙句、人間を怒りっぽくするそうです。
ストレス過剰の現代では、怒りっぽい人が激増するのも当然かもしれませんが…
怒りに支配されると物事を見誤る可能性が高く、不利益を被ったり幸福や満足を感じにくくなったりするそうです。
感情を制御し冷静でいられる能力は、物事を正確に捉えて的確な判断を下すことにも繋がるので、
現代社会を生き抜くためには、特に重要な能力といえるのかもしれません。